エルスウェーニョの新着情報やお知らせ、
ブログをご覧ください。

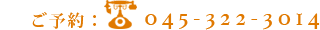


エルスウェーニョの新着情報やお知らせ、
ブログをご覧ください。
横浜駅イタリアンレストラン・エルスウェーニョでのビッキーとユーリのグルメ探訪(2)
ビッキーとユーリは、また横浜駅イタリアンレストラン・エルスウェーニョへ行きたくなった。
アンティークで重厚な店内の造り。
できては消え、できては消える横浜駅周辺のレストランにはとうていかもしだすことのできない三十年の歴史の重み。熟成した雰囲気。
店主や店員の人柄。おいしい料理。お酒。
ジャズの生演奏。
「またいきたいな。」
すぐ行ける。横浜駅から歩いてすぐだ。
休みはない。店は毎日開いている。
ビッキーとユーリは再度
横浜駅イタリアンレストラン・エルスウェーニョを訪れた。
入り口に足を踏み入れるとなつかしい感じがした。
もう何度も来ているなじみのお店のような。
そして子供の頃行ったいなかのおばあちゃんの大きな家のような。
前回と同じ店員が
「いらっしゃいませ。またお越し下さってありがとうございます」
と笑顔でむかえてくれた。覚えていてくれたのだ。
「今回は違うお部屋にどうぞ」と案内してくれた。
あの大きな一枚板のカウンターと大きな丸太の梁を右に見て、グランドピアノのあるホールの手前を左に折れる。しっくいの壁が丸く囲んだ中くらいの部屋がある。テラコッタの床と頭の上にガレーのシャンデリアが下がっていた。
「素敵な部屋だな。十人くらいのパーティにちょうどいいな」と思って部屋に入ると
驚いたことにその部屋の奥にもう一つの部屋があった。
こちらも丸いしっくいの壁が囲み、床はオークの無垢の板張り、丸い大きめのテーブルと長イス
そしてその横に小さい暖炉が掘られている。
「ステキ、秘密の部屋みたい」
とユーリが言う。
座って上を見るとアイボリ色の天井は教会のようにドーム状に丸くつくられている。
窓に厚いガラスがはめられ、絵が彫られている。花瓶の絵の上にラリックという名をみつけて、フランスのガラス彫刻家のラリックかしらと思う。
こんなに厚くてすてきな硝子は見たことない。
そういえば前回の小部屋もこんな厚くて大きくてカーブを持っているガラスで仕切られていたな。
ビッキーとユーリがそんなおしゃべりをしているうちに江野がやってきた。
「やあ、いらっしゃい。また来てくれてありがとう」
とメニューを渡す。
ビッキーとユーリは江野に会うのがたのしみだ。
もうだいぶ年とも思われるが、体の姿勢もいいし、体型も若者のようにひきしまっている。
歩く姿や動きもキビキビしている上、ものごしが優雅で見ていて楽しい。
「いい年齢の重ね方をしてきたんだろうな」
とビッキーは思う。
料理の仕事は体が資本である。
毎日、長時間、立って仕事をする。
長時間立っていられるためには姿勢が大事だ。
正しく美しい姿勢を保つためには足腰を鍛える必要がある。
江野は通勤に山の坂道を片道四十分かけて歩く。
三十年近く毎日歩く。山の公園の木で懸垂し、体操する。
イタリアンレストラン・エルスウェーニョが横浜駅の近くにできてから一日も欠かしたことがない。
メニューを見ながらユーリが
「このカルチョーフィって何ですか?」
と聞く。
アーティチョークとも呼ばれるカルチョーフィはイタリアには普通にたくさん生えている。
アザミの紫の大きな花をとって花びらやガクをとりのぞき、特上の花芯をソテーにする。
あるいは煮込む。季節のものなのでたくさんつくってマリネで保存する。
イタリアの一般的な家庭では普通に食べられている。イタリア人の大好物だ。
「じゃ食べてみよう。あと生ハムの、この幻の生ハムとそれから赤ワインのボトルをお願いします。」
とビッキーが注文する。
江野が持ってきたワインはイタリアのバローロだ。
イタリア北部のピエモンテ州の代表的なワインだ。
ピエモンテのバローロとバルバレスコは
イタリアンワインの王様と女王様と呼ばれている。
愛称のとおり、バローロは力強い男性的な味わいがあり、バルバレスコは優雅なおいしさである。
特にこのほかの特産で味覚の王様トリュフと共に味わわれている。
そんな話をビッキーとユーリにとつとつと語りながら、江野はソムリエナイフであざやかにバローロをあけ
まずはビッキーの背の高くて薄いワイングラスに少量注ぐ。
ワイングラスの口は少しつばまっている。
ワインの香りを保つためだ。
「ワイングラスをすこし回して赤ワインを空気にふれさせてから香りを嗅いでください。」
とアドバイスした。
赤ワインのボトルからデキャンタに移して空気にふれさせる。
デキャンティングという方法もある。あるいは予約を受けて何時間か前に抜染しておく方法もある。
そのように赤ワインを空気にふれさせて香りが大きくなることを「ワインが花ひらく」と呼ぶ。
それからビッキーに一口味わってもらい。
「いかがですか?」と問いかけ
ビッキーは「とてもおいしいです」と答える。
それからユーリのグラスに注ぐ。それからビッキーへ。
ワインのテイスティングと呼ばれる儀式だ。
ビッキーとユーリは「乾杯!」
といってグラスを重ねてバローロを味わう。
「おいしい」とユーリはニッコリと
ビッキーと江野に微笑みかける。
幻の生ハムが来た。
皿にスライスして盛られているだけで
おいしそうな独特の香りを放っている。
「クラテッロ・ディ・ズイベロ」
イタリアのエミリア・ロマーニアを流れるポー川の上流の小さな村、ズイベロ村でしかつくられていなくてイタリア以外ではもちろん、
イタリアの人達でさえ、なかなか口にすることができない希少な生ハムだ。
別名 幻の生ハム。
製法は永らく秘伝であった。
霧深いこの山奥の村で、昔から村人の間でひっそりとつくられていたのだ。
まだビニール袋などない時代。
水を入れて持ち運ぶ皮袋に牛のボウコウ(膀胱)が使われていた。
雌の豚のおしりの肉を雄牛のボウコウに詰め込んでヒモで網状にしばりあげる。
それを洞窟にずらりとつり下げる。
毎日、床にワインを撒きキハツ(揮発)したワインを
皮と肉に吸わせる。
そのようにして熟成させる。
ビッキーとユーリも初めて食べる幻の生ハムのそのおいしさ、秘密めいた味、遠い時代、はるかな土地を思わせる味にことばもでない。
遠いイタリアの山奥の地へ思いを馳せる。
バローロがいちだんとおいしくなった。
次のお皿はカルチョーフィと煮込み野菜のサラダだ。
大きめの皿にサニーカールやルッコラの生野菜が盛られ、周りにカルチョーフィ、トマト、セロリ、パプリカ、ピーマン、ナスなど煮込んだ野菜が盛られている。
生野菜にかけられているドレッシングソースは、江野のオリジナルで少し和風のテイスト。どうやってつくるんですか?とよくお客様から尋ねられる。
江野は野菜のおいしさをひきだすのは
とてもむずかしいと思っている。
江野の子供の頃、家の前の畑にはいろいろな野菜が実っていた。真っ赤に熟したトマトにかぶりつく。
夏の香りと太陽の味。曲がったキュウリをボキッと折りガリガリ食べる。青い香りがあたりに広がる。
甘く青い味。
野菜だけではない。山には生まれたばかりの柔らかいタケノコ。朝ひらいたばかりのシイタケ。地中に長く伸びた大きなヤマイモ。
自然の恵み、味、おいしさをそのまま直接食べていたのだ。
海の幸も海から直かにもらう。
遠浅の干潟で砂を熊手で掘ると大きなアサリやハマグリがゴロゴロ出てくる。あさりは海に戻して大きなハマグリだけをバケツにいっぱい持って帰る。
今晩の食卓にのぼる。
江野は現代の野菜、魚、肉などは総じて
味と香りが薄くなってきていると思っている。
それらの食材の本来持っている豊穣な味と香りを引きだすことが料理だ。
調味料ではない。
自然を引き出す方法。
イタリア料理では野菜はバーニャカウダーなどにして食べられる。
ソースはアンチョビ、にんにく、チーズ、オリーブ油、牛乳、生クリームなどを煮込み暖かくして生野菜にかけて食べる。
だがその生野菜がいま出まわっている味の薄い野菜だとしたら?
店ではラタトゥイユと呼んでいるカポナータは伝統的野菜煮込み料理である。
イタリアだけでなく地中海地方では一般的な家庭料理だ。
いろいろな野菜をいろいろな方法で煮込む。
日本の味噌汁と同じくおふくろの味なのである。
ビッキーとユーリの食べている煮込み野菜は
江野が毎日煮込むラタトゥイユで、イベリコ生ハムのラルドとオリーブオイルでゆっくりと野菜をソテーし、
そのまま塩味だけでゆっくりと煮込むだけで、水やダシは入れない。
ビッキーとユーリははじめて食べるカルチョーフィだけでなく、食べなれているナスやパプリカなどがこんなにもおいしいのかと
目が覚めるような気がした。
横浜駅イタリアンレストラン・エルスウェーニョでのビッキーとユーリの今夜のおめあては
はじめから決まっている。
ラザニアという素晴らしいイタリア家庭料理がある。
各家庭に各ラザニアがある。
材料として小麦粉、トマト、野菜、肉、牛乳、生クリーム、チーズというふうにほとんどすべてを使う。
調理方法も水で茹でて火で焼く。
二重においしさを増幅させるのだ。
江野はイタリアの大きい農家の主婦シルバーナのつくるラザニアが最高だと思っている。シルバーナは毎日、家庭や小作人たちに食事をつくっていた。
ラザニアは平べったいパスタをゆで、
ホワイトソースとトマトのミートソースをパスタの間にはさみ重ねて、オーブンで焼く。
形は自由で、丸くも四角もできるし、
重ねる段の数も自由である。
パスタ生地にもいろいろな材料を混ぜることができる。ラグーと呼ばれるミートソースの材料はなんでも使えるし、
ホワイトソースもいろいろな方法がある。
ベシャメルと呼べれるバターと小麦粉をゆっくりとソテーし、牛乳で暖かくきめ細かくのばしてゆくホワイトソースが一般的であるが
江野は独特のホワイトソースを生み出した。
古来、イタリアでは栗の実やクルミのみが小麦粉のかわりにホワイトソースとして使われていた。
それを取り入れている。
パスタも普通レストランなどでも使われている乾燥した板のようなラザニアを水でもどしてから重ねてオーブンで焼くというものではなく、
小麦粉を練って伸ばす生パスタを広たく形つくって、そのつどゆでる。
温めた自家製のホワイトソース。パスタ、ラグー、パスタと交互にゆでては重ね、四枚重ねる。
二人前ならこれくらいだ。
上にチーズとホワイトソースを重ね
炭火で焼く。
ビッキーとユーリの前に置かれたラザニアは焼きたてで、ソースがグツグツと煮えかえっていた。チーズをはじめ材料の香りが広がる。
「おいしそう」
お皿が熱いから気をつけなくては、
カットされた一切を小皿にとってすこし冷まして口へ運んだ。
「おいしい」
二人は顔を見合わせた。
イタリアの古き良き家庭の情景が浮かんだ。
家族がいて暖炉が燃えて、木のテーブルでおかあさんの作ったラザニアを子供たちがフーフーいいながら食べている。
そんな暖かい家庭、暖かい味だった。
第二章おわり
20 × 20
