
横浜のジャズバー・エルスウェーニョ 心温まるイタリアン・スパニッシュ料理とともに 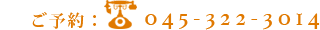
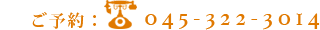

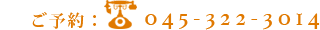


何十年もの間、ボトルの中でしずかに眠っていて出番を待っている。後の生命の輝く瞬間を待っているのだ。
今、ワインは長い眠りから覚めた。
「おや、ここはどこだ。故郷より少し湿っぽいようだ。海の香りがする。どれくらい眠っていたのか。目の前に若く美しい東洋の女性が微笑んでいる。この人に飲まれるのか?最高だ。隣に妙な男が二人いるがまあこれはよしとしよう。覚こしてくれたのはこの美青年か。なかなかわたしのことをわかってくれているようだ」
女性が顔を近づけてきた。ドキドキ。ワインは細胞をいっぱいにふくらまし空気をとりこみ、その芳香を力の限り放つ。
「いい香り」
舞は鼻で吸い込んで、あまい吐息を吹きかける。ワインは生命の最高の瞬間への期待で震える。舞の唇が触れた瞬間、ワインは波立ち、口の中へ飛び込んでゆく。舌の上でころがされ、恍惚としてのどの奥へ流れ込み、そして落ちてゆくワインの花道。ワインのおいしさを表現することはできない。
「美味しい」
と舞はため息をつく。
高も純も述も
「美味しい」
と言う・
甘い、酸っぱい、苦い、辛い、渋い、いろいろの味の織りなすタペストリーボディが重いという。生命のちからがあふれていることだ。