エルスウェーニョの新着情報やお知らせ、
ブログをご覧ください。

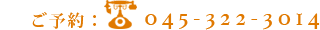


エルスウェーニョの新着情報やお知らせ、
ブログをご覧ください。
- エル・スウェーニョ 横浜駅 ジャズアンドイタリアンレストラン ビッキーの論説 ギリシャ神話 第二章 神々の概観
後編
とにかく、ギリシャの神々は、人間らしいという点でその宗教性が批判されてきた。
特にキリスト教のごとく、自分の教義だけが心理であるとする全く不寛容な宗教が世界の多くを支配すると、それまでにあった、ギリシャの神々のような多神教はただちに虚偽で険悪するべきものとされた。
さらに、宗教学の方面ではギリシャの神々が姿を持つものとして存在し、神殿や彫刻などで偶像として崇拝される点で、キリスト教の立場からされてきた。
例えばヘーゲルの「歴史哲学講義」から引用すると、
「キリスト教と比較して、ギリシャ宗教の真の欠陥は、キリスト教においては現れるということが、神的なものの一つの契機として想定されているのに過ぎないのに、ギリシャ宗教においては、現れるということが最高の存在様式であり、実に神的なるものの全体をなしているということである。
キリスト教においては、現れたる神は死し、自己を止揚するものとして定立されている。
キリスト死して初めて、神の右手に坐せるものとして示される。
これに反してギリシャの神は、ギリシャ人にとって、現れのうちに永続的に存在するものであり、大理石や金属や木材のうちに、または空想の像として表像のうちに存在するにすぎないのである。」
なるほど主なギリシャの神々はその姿をはっきり見ることができる。
最初は詩の描写によって、そしてそれをもとにして彫刻、絵画によって、はっきりとした姿が描かれている。
このように神が姿を持つことが、宗教性の面で欠点となるかどうかは立ち入ることができないが、後のゲーテはアポロン像の前に立った時、崇高な神の光を見出したと言われているし、ゲーテのごとく高貴な精神が、ギリシャの神々の姿に神的なものを見るという例は、シラーやバイロンやその他多数の人々にも共通しており、また、我々日本人にとっては仏像に崇高な宗教性を見るというような例もあり、必ずしも、ヘーゲルのことばがすべて正しいとはいえないと思われる。
古代ギリシャでは、神々に捧げる多くの祭儀が生活の中で生きており、紀元後一世紀のころ、使徒パウロはアテナィを訪れ、多くの偶像に憤りを感じたけれど、当時のギリシャ人があらゆる面で非常に宗教心に富んでいることに驚嘆している。
ゲーテも、ホメロスは、いつも神々との関係を保っていたのに対し、当時(中世)にキリスト教のしきたりがあったとはいえ、これらの人々には天上の光の反映は微塵も見られないと語ったと伝えられる。
つまり、古代ギリシャ人が敬虔という意味で、神に負うもの、神に帰属するものが、日常の生活の中で非常に大きかったといえるのである。
古代ギリシャ人は、人間の行動を決定するものを神々と信じていた。
それはホメロスの詩の中に最もよく表れたいる。
「イリアス」の中で、アキレウスは追いつめたヘクトールに、
「もう、おまえにはのがれる道は一つとしてないのだ。すぐにもおまえを、パラス・アテナが私の槍で討ちとるであろう。」
と語る。
自分が行為するのではなく、アキレウスにおいてはアテナが行為するものとされるのである。
我々なら自分自身の決断というべきところで、ホメロスはある神の出現を見る。
その時代のギリシャ人一般にも同じことがいえるのであり、つまり神々は、自然現象や運命的な事件に現れるだけでなく、人間をその内奥で動かすもののうちにも現れると考えられていた。
同じことが詩人たち自身にもいえる。
叙事詩は数百年の伝統的な言語技巧をもってホメロスによって完成されるが、ギリシャの神々は、まず最初に、詩人たちに、ムーサ女神たちによって啓示された。
ムーサ(ミュージックの語源)たちは、神話では野や山に住み、アポロンと共に詩と音楽を司る女神である。
古代では詩と音楽は密接な関係にあり、詩人は、ムーサの「下僕」と自ら名のり、詩人の口から語られる口唱叙事詩は、すべてムーサが詩人の口をかりて歌うとされていた。
「イリアス」の冒頭の句も、「怒りを歌え、女神よ、ペーレウスの子アキレウスの」と、ムーサへの呼びかけからはじまる。
ヘシオドスも、ムーサが彼のもとにやってきて、聖なる歌を吹き込んだと語り、以下神々の系譜を「神統記」において語る。
ホメロスやヘシオドスのごとく、詩人たちは自分が詩をつくるのではなく、ムーサ女神が歌うのだと実際に考えていたのだ。
これからのことは、現代の我々には理解しがたく、またそのような態度を崇高なもの認めにくいものであろう。
そこで次の文を引用したい。
「ギリシャ的人間は神々に満ちた世界に在るので、自己の内部に視線をそらせ、そこに行動の動機と責任の根源を求めたりはしない。
彼の視線は存在の偉大なる事物に向かって注がれ、我々が志操だとか意志だとかいうときに、いつも神々の生きた実在(レアリアート)に出会っている。
このことから心理学者たちは、彼らの概念は実存(エクシステニス)の狭い領域にまったく閉じ込められている馬鹿げた結論を引き出す、当時の人間は未だ精神的内面生活の深みを知らなかったのだと。
真実はといえば、ギリシャ人は実在の世界を、つまり一切の存在(ザイン)を内にたもつ神々を生き生きと経験することによって、現代では学問さえなかった自己投影の危険と禍いとに対して守られていたのである。
それゆえにこそ、ホメロスをはじめとするギリシャのすべての偉大な人物たちに見られる、あのような高邁な精神状態が生まれえたのである。」W・F・オットー「神話と宗教」
ムーサ女神によって神々は初めて詩人たちに姿を現した。
詩人たち以前のギリシャ人には神の名と祭儀があっただけだったが、ホメロスと(シオドスが神々の由来や姿を描いて、それがギリシャ神話を形成していたっと伝えたれる。
ムーサのような若く美しい女神が告げる神々は、寛容で、威圧的なところは全くなく、神々の名において説く教義や聖典というものは存在せず、人々は神々に対する敬意を忘れなければ、神々をどのように考えようとかまわなかったにもかかわらず、これらの時代にほとんど不信仰は存在しなかったといわれている。
しかしながら、その後キリスト教が宗教世界で勝利をおさめるとともに、ギリシャの神々は軽蔑され、無視されてしまう。
この時の事情をニーチェはこう語る。
『その事件が起こったのは、このうえもなく神をなみすることばが一人のかみそのものによって言われた時である。そのことばというのはこうだ。
「神は一人あるだけである。おまえはわたしのほかにいかなる神をもいただいてはならぬ」
髯の濃い怒りの神、嫉妬の神が我を忘れてこう言ったのだ。
それを聞いて、神々のすべては哄笑し、めいめいの椅子を揺すぶって叫んだ。
「神々はあるが、唯一の神はいない。そういうことこそ神的なことではないか」と。』
神的なこととは?
絶対の主権、絶対的屈従の要求、嫉妬、不寛容、これらは真実人間的なことではないのか?
そして事物の存在の多様性にこそ、神的なものをギリシャ人は見た。第二章 おわり
