エルスウェーニョの新着情報やお知らせ、
ブログをご覧ください。

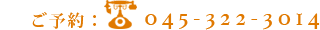


エルスウェーニョの新着情報やお知らせ、
ブログをご覧ください。
横浜駅イタリアンレストラン・エルスウェーニョでのビッキーとユーリのグルメ探訪(6)
ユーリはお肉が大好きである。
今度、横浜駅イタリアンレストラン・エルスウェーニョに行ったら、絶対イベリコステーキを食べようと思っている。
できては消え、できては消える横浜駅周辺のレストランの中で三十年近く続けているイタリアンレストラン・エルスウェーニョの絶品肉料理である。
人間が草食動物か肉食動物であるか議論の別れるところかもしれない。本来、ジャングルの木の上で暮らしていた人間の先祖がサバンナに降り立ち、手に槍と火を持つことによって、ライオンのように鹿を食うようになったのだ。
槍で鹿を追う人間は、世界中に広がり
鹿だけでなくマンモスまでも追いユーラシア大陸を旅し、陸続きのカムチャッカを渡りアメリカ大陸を北から南まで旅する。
あるいは魚を追ってコンティギ号のように大津波を渡る。
年月が立ち、やがてカメリーナをつくる人々、お米をつくる人々、羊の群れについてゆく人々がでてくる。
鳥や鶏の肉もよく食べられたし、
マホメットが禁ずるまで豚肉は世界中で食べられていた。
牛の肉はそれほどではなかった。
イギリス人のことをビーフィーター、つまり牛肉を食べる人と呼ぶのは一種の蔑称であった。
日本では動物を追う必要はなく海に魚や貝があふれていた。
仏教の教えでは食べることを殺生という。
人間が食べるという事は他の生きものを殺すことだ。
なるべく食べないようにしなければならない。
でも食べなければ自分が死ぬ。
で、手を合わせて「いただきます」と祈ってから食べる。
他の命を食べるのだ。
日本では永らく肉食は禁止されていた。
東京オリンピックで日本柔道がヘーシングに負けたのは肉を食べないせいだという政府の見解に基づいて、学校給食に肉がどんどん登場した。
鯨の肉である。
ハーマン・メルヴィルの不朽の名作「白鯨」では真っ白いマッコウクジラにたたきのめされ
片目片腕片足を失ったエイハブ船長が復讐に燃え、モービル・ディックを追って七つの海を渡る。
アメリカは太平洋の鯨を取りつくすため
蒸気船で日本までやってきて徳川幕府に
開港をせまる。捕鯨船の補給のためである。
土佐や紀伊の太地の村では、鯨を追う小舟のへさきに、もりうちの男が立つ。
一発で鯨をしとめれば、男は英雄となり
村はうるおう。
日本が捕鯨船で太平洋の鯨を取りに乗り出したころには鯨はだいぶ少なくなっていて、
まもなく世界中から鯨を絶滅させる悪者として
ふくろだたきにされることになる。
日本人が鯨の肉をたらふく食べた期間は短かかった。
「緑の革命」と呼ばれる農業技術、放逐技術の発達にともなって現代では食品があふれている。
肉も日常普通に食べられている。
だが肉自体の味は薄くなってきているように江野は思われる。
無味無臭に近づいてきているのだ。
イタリアのトスカーナのキアナ谷というところに
とてつもなく大きくて真っ白い牛がいる。
古代種の牛である。
その牛の背中の肉、ロースとフィレを横に骨ごと切る。
Tの形の骨に分厚い肉がはさまっている。
家畜をと殺するときはこわがらせてはいけない。
散歩するように連れてきてすぐに眠らせる。
家畜がこわがると恐怖のアドレナリンが肉に充満し、味が落ちるのだ。
肉を解体した後もすぐには切らずに大きなかたまりでつるしたまま熟成させる。
どれくらいの期間の熟成がその肉に最適であるかは肉職人の腕と感によるしかない。
熟成が進み、肉が最もおいしくなった時、
Tの時に分厚く切り、暖炉に火を入れる。
甘い香りのするクリの木やコナラの木を燃やす。
木が燃え、真っ赤なおき火になったころあいを見て、肉を火の上の五徳(網)に乗せる。
塩、胡椒はしてはいけない。
策に塩、胡椒をすると肉の柔らかみが失われるのだ
火の強さ加減と肉との距離で焼き加減が決まる。
職人の腕のみせどころである。
表の片面を強火で焼き、表面を固形させて
肉の汁を中に封じ込めて、味を逃がさないようにする
裏面も同じだ。それからゆっくりとミディアムレアに
火がとおるように焼く。焼きすぎても焼き足りなくてもいけない。焼き上がると塩と胡椒だけでいただく。
ビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ
ビッキーとユーリは今夜も横浜駅から歩いてイタリアンレストラン・エルスウェーニョに訪れた。
いつもの店員、いつものシェフ、いつものカウンター、いつもの店内、いつもの光だ。
でも今夜はピアノはホールの真ん中に置かれていて、ピアノを回っていちばん左の奥のテーブルに座った。
レンガの壁にくっついたテーブルだ。奥まった感じで店内がすこし違って見えた。
江野がやってきて
「やあ、ビッキー君とユーリさん、こんばんは」
と迎えてくれた。
「今夜はどうします?」
「お肉が食べたーい」とユーリが甘える。
「じゃあイベリコステーキがいいかな」と江野。
「では、ステーキとサラダと、カメリーナをつけて、
あと赤ワインがいいな」
とビッキーが言う。
江野はカメリーナと呼んでもらえてうれしかった。
まずは赤ワインのボトルを江野が二人のテーブルで開ける。イタリアのプリミーティーボである。
トスカーナの南の山地のウンブリア州のワインだ。
ローカルでいなかじみた感じの印象の味がいい。豊かな味だ。
土の香りがする。
シェフのおまかせサラダが運ばれた。
大きな深いお皿にサニーカールとルッコラが盛られ周りに色とりどりに野菜が並らんでいる。
「きれい。」とユーリが言う。
真っ赤なトマト、赤、黄、オレンジのパプリカ、緑のピーマン、白い玉ねぎ、セロリ、オレンジ色のにんじん、茶緑のカルチョーフィ、紫色のナス、どれも江野が毎日煮込み、味を引きだし
味をととのえた野菜たちだ。
「このドレッシングおいしいわあ。
どうやってつくるのか聞いてみようかな」
とユーリが言うのをビッキーが制して、
「だめだよ。そんなこと聞いちゃ
プロの料理人の技術なんだから」
と言う。
イベリコステーキとカメリーナが来た。
ステーキは大きめのアンダーソーサーの上の熱せられた白い皿の上で、こげ茶色のソースがジューと音を立てていた。
このソースは江野がイベリコ生ハムの骨を一週間かけて煮込んでつくるオリジナルだ。
ナイフでステーキの肉を切ると厚みのある肉はうっすらとピンク色を漂わせる白い色で
ちょうど火がとおって焼きすぎない絶妙の焼き加減だ。
豚肉なので生ではいけない。焼きすぎても硬くなる。
一口食べてユーリは
「おいしいいい」と一言言って
もう一口食べる。
イベリコ豚はイベリア種というスペイン原産の黒豚だ。
野生の獣の香りをもつ。
現代の無味無臭の肉とは別物のような味だ。
ユーリはこういうものが好みだ。
赤ワインといっしょにふりかけて仕上げるソースは
濃厚なおいしさでここでしか味わえない。
カメリーナにつけて食べるとこれがまた最高である。
横浜駅イタリアンレストラン・エルスウェーニョのいちばん奥の奥のテーブルで、ビッキーとユーリの幸せな時間が過ぎてゆく。
ジャズの演奏が始まった。今夜はピアノのソロの演奏だ。「ミスティ」の曲がながれる。
ユーリはミスティックでロマンチックな気分で大好きなビッキーをながめていた。
第六章おわり
20 × 20
